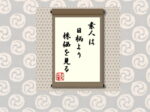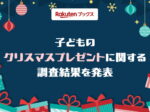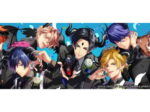- Home
- 小倉正男の経済コラム
- 【小倉正男の経済コラム】パウエルFRB議長「12月利下げは既定路線ではない」雇用低下で連続利下げ、だが12月FOMCはインフレ警戒に軸足
【小倉正男の経済コラム】パウエルFRB議長「12月利下げは既定路線ではない」雇用低下で連続利下げ、だが12月FOMCはインフレ警戒に軸足
- 2025/11/4 13:58
- 小倉正男の経済コラム

■2会合連続利下げ、対極的立場から2名が反対
米連邦準備制度理事会(FRB)は、10月末の連邦公開市場委員会(FOMC)で0.25%の利下げを決定した。9月FOMC(0.25%利下げ実施)に続いて2会合連続利下げを行ったことになる。政策金利は3.75%~4.00%に引き下げられている。
10月FOMCでは10名の当局者が賛成、2名が反対している。反対を表明した一人は、大統領経済諮問委員会委員長から転身したスティーブン・ミラン理事だ。8月に欠員を利用してトランプ大統領がFRB理事に押し込んでいる。ミラン理事は「トランプ関税」の推進筆頭格だが、住宅不況=景気後退を理由に連続して0.5%利下げを主張している。
反対したもう一人は、カンザスシティ連銀のシュミッド総裁である。9月0.25%利下げには賛成したが、今回はインフレ警戒に重点を置き利下げに反対している。いまの雇用低下は景気に関連したものでなく、利下げを行っても改善効果はない。インフレはFRB目標(2%)を長期間上回っており、その現実は連続利下げを正当化できない――。
■マーケットに近いサイドはインフレ警戒を発信
関心はすでに12月9~10日の次期FOMCのほうに移っている。パウエルFRB議長は、「12月会合での追加利下げは既定路線ではない」と発言。しかも、「そのような状況とは程遠い」と3会合連続の利下げにむしろ否定的な立ち位置を表明している。
パウエル議長は10月FOMC直前には「失業率が上昇に転じる地点に近づいている」と雇用悪化=景気後退のリスクを強調する発言をしている。大方は3会合連続の利下げ予想に傾いていたのだが、パウエル議長はそれを少なくとも「白紙」に戻したわけである。
12月FOMCでは、カンザスシティ連銀・シュミッド総裁のインフレ警戒に轡を並べるメンバーが増えるとみられる。FOMCメンバーではない各地区連銀総裁などから10月FOMCの2会合連続利下げに賛同できないという意見も相次いでいる。
9月消費者物価指数(CPI)は前年同月比3.0%増。不思議なことに「トランプ関税」によるインフレを顕在化させる指標にはなっていない。だが、それでも「現状は十分にインフレ」という見方が各地区連銀から表明されている。つまり、マーケット現場に近いサイドからインフレ警戒が発信されている。
■消費者物価指数と消費現場実感との齟齬
各地区連銀総裁筋などは、個人消費は堅調、設備投資はAIブームからデータセンター建設・機器納入が活発化している。それなのに雇用低下になっているのは、移民など人口動態の構造変化、ICT・AIなど技術革新によると推定している。景気は弱いどころがむしろ強い――。利下げを行えば、インフレを加速する懸念があるという見立てである。
ちなみに日本のこの9月消費者物価指数(総合)は、前年同月比2.9%増である。コメ、チョコレート、おにぎり、コーヒー豆、鶏卵など食料品が軒並みに大幅上昇となっている。一方で高校授業料など教育費は大幅に低下している。米国の9月消費者物価指数3.0%増とほぼ同様の格好、消費者物価指数と消費現場の実感とは齟齬が生じている可能性がある。
トランプ大統領サイドからは当然ながら異なった意見が語られている。ベッセント財務長官、ミランFRB理事などは、「高金利で住宅市場は景気後退(リセッション)に陥っている可能性がある」と追加の連続利下げを再三催促している。
トランプ大統領サイドとしては、利下げの加速で景気を浮揚して新年11月の中間選挙を迎えたい。トランプ大統領の支持率は下降気味であり、利下げはそのテコ入れ策として不可欠なステップにほかならない。12月FOMCが接近すれば、トランプ大統領が直接乗り出してパウエル議長に露骨な圧力を加える局面も想定される。
そうした事態は政権に対するFRBの独立・中立性が、曲がりなりにも保たれている現状にある証明である。12月FOMCはインフレ警戒に軸足を移し3会合連続利下げを見送る可能性が強いのではないかとみられる。パウエル議長の任期は26年5月、トランプ大統領との軋轢は最終コーナーに突入する。(経済ジャーナリスト)
(小倉正男=「M&A資本主義」「トヨタとイトーヨーカ堂」(東洋経済新報社刊)、「日本の時短革命」「倒れない経営~クライシスマネジメントとは何か」(PHP研究所刊)など著書多数。東洋経済新報社で企業情報部長、金融証券部長、名古屋支社長などを経て経済ジャーナリスト。2012年から当「経済コラム」を担当)(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)