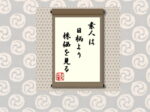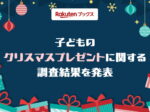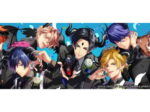【日本造船業、復権の航路へ】高市政権が掲げる国家戦略の中核に、官民3500億円投資で国際競争再挑戦
- 2025/11/2 07:47
- コラム

■アンモニア燃料・AI航行など次世代技術で再成長へ
日本造船業界4団体が国土交通省と自民党政策部会に提出した政策提言が、業界再生への号砲となった。高市早苗政権の成長戦略では、造船・舶用機器分野を「国家安全保障と産業競争力の両輪」と位置づけ、官民で3500億円規模の投資支援を進める方針が示された。提言は、2035年までに建造能力を現行の2倍、約1800万総トンへ引き上げることを目標とし、1兆円規模の基金創設構想も盛り込まれた。輸出入の99.5%を海上輸送に依存する日本にとって、造船業の自立的回復は経済安全保障上の急務である。
■技術革新とグリーンシップの波
脱炭素化の潮流が造船分野を変えている。日本郵船<9101>(東証プライム)、三菱重工業<7011>(東証プライム)、川崎重工業<7012>(東証プライム)が主導するアンモニア燃料船の開発は、CO2排出ゼロを実現する次世代船として注目を集める。さらに、ダイハツディーゼル<6024>(東証スタンダード)やヤンマーホールディングスがLNG・水素燃料推進システムを推進し、自律航行やAI制御を活用する「スマートシップ」構想も進展している。造船受注量は2024年後半から回復傾向にあり、グリーン燃料関連が全体の3割を占め始めた。日本の技術力と政策支援が結びつくことで、アジア勢に奪われた市場競争力の回復が現実味を帯びてきた。
■政策支援と株式市場の反応
自民党政策部会では「次世代造船・舶用技術育成基金(仮称)」の設立が議論され、経済産業省と国土交通省は「グリーン船舶認証制度」の国際標準化を主導している。政策期待を背景に、三井E&S<7018>(東証プライム)、今治造船、ジャパンマリンユナイテッドなどの造船大手に加え、ナブテスコ<6268>(東証プライム)、シンコー<6134>(東証スタンダード)、川崎重工舶用部門などの舶用機器関連株が相次いで高値を更新した。円安による採算改善、受注拡大、脱炭素技術の優位性が投資家の評価を押し上げている。市場では「造船株がバリュー株の新たな主役に浮上する」との見方が強まっている。
■再戦略産業としての再出発
防衛・海洋安全保障の需要拡大が続く中、IHI<7013>(東証プライム)や三菱重工など防衛関連企業も恩恵を受けている。洋上風力や海底ケーブル敷設など再生可能エネルギー関連の特殊船需要も上昇しており、造船産業はもはや単なる製造業ではなく、エネルギー・安全保障・デジタルを結ぶ結節点となりつつある。熟練技術者不足への対応として、AI設計支援やデジタルツイン化も進展中で、日立造船<7004>(東証プライム)が設計DXソリューションの拡販を進めている。政府と企業が一体で挑む造船再生の航路は、2026年以降、日本の産業構造転換を象徴する動きとなる可能性が高い。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)