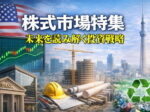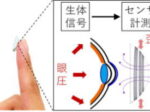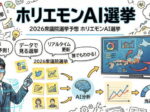江戸の暮らしを1/10スケールで再現、檜細工師・三浦宏の作品展開催中
- 2025/11/27 16:18
- 話題

■檜細工でよみがえる江戸の町、三浦宏の精緻な世界、今ここに
かつて江戸の庶民が汗を流し談笑した「湯屋」の熱気まで伝わってくるようだ。東京都台東区の台東区民会館で、浅草出身の檜(ひのき)細工師・三浦宏さん(1926~2019)の手による江戸期の家屋復元模型を展示する「三浦宏作品展 小さく拵(こしら)えた江戸の町並み」が開催されている。
家業の風呂桶作りで培った技術と、徹底した時代考証によって再現された「小さな江戸」が、訪れる人々を魅了している。
■息づかい感じる精巧な造り
会場には、三浦さんが制作した縮尺1/10の模型6点が並ぶ。本展の目玉の一つが、庶民の社交場であった銭湯を再現した「湯屋(ゆや)」だ。江戸時代の風呂は蒸気を逃さないよう、湯船の前面が「石榴口(ざくろぐち)」と呼ばれる板戸で覆われているのが特徴で、内部はサウナのような状態だったという。作品ではこうした構造はもちろん、湯上がりに将棋などを楽しんだ二階の休憩所まで精巧に作り込まれている。このほか、呉服屋、火の見櫓(やぐら)、床屋など、江戸の町並みを構成する建物が展示され、当時の人々の暮らしや息づかいを感じ取ることができる。
■風呂桶職人から模型作家へ
作者の三浦さんは大正15年(1926)、浅草の風呂桶職人の家に生まれた。父や船大工の祖父から受け継いだ技術で檜風呂などを製作していたが、時代の移り変わりとともに木製風呂桶の需要が減少。その中で、空いた時間を利用し、子供の頃から親しんだ和船の模型作りを始めたのが創作の原点だ。昭和50年代には、人形作家・辻村寿三郎氏の依頼で吉原の妓楼(ぎろう)を制作したことが大きな話題となり、以降、亡くなるまでの38年間に100点以上のミニチュア作品を残した。
■同フロアでは、大河ドラマ館も開館中
作品展は、台東区民会館9階ロビー(東京都台東区花川戸2-6-5)で、2026年1月12日まで開催(一部休館日あり)。開場時間は午前9時から午後5時まで、入場無料となっている。
なお、作品展と同フロアでは、2025年放送の大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」の世界観を楽しめる「べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館」も開館中(有料、大人800円ほか)。主人公・蔦屋重三郎の衣装や舞台地・台東区に関するパネル等も展示されており、あわせて見ることでより深く江戸・台東区の文化に触れることができそうだ。主催は、台東区大河ドラマ「べらぼう」活用推進協議会。
また、近隣の台東区立一葉記念館(東京都台東区竜泉3-18-4)では、現在開催中の特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」にて、三浦氏による「下谷龍泉寺町 樋口一葉旧居模型」も展示されており浅草散策とあわせての鑑賞も楽しめる(12月21日まで)。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)