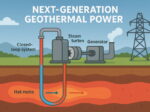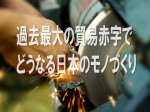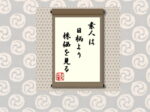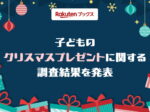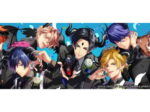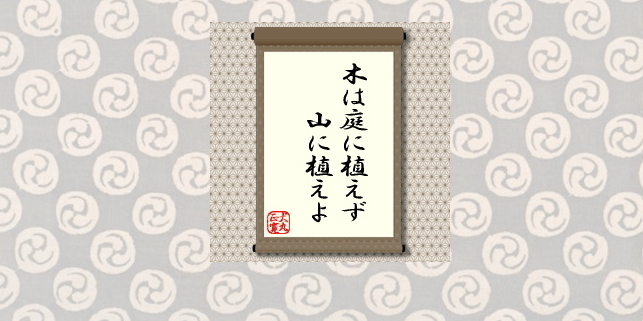
【先人の教えを格言で解説!】
(犬丸正寛=株式評論家・平成28年:2016年)没・享年72歳。生前に残した相場格言を定期的に紹介。)※最新の情報に修正を加えてあります
■木は庭に植えず山に植えよ(焦らず見守る投資姿勢)
「木は庭に植えず山に植えよ」。気に入った苗木を買って身近な庭に植えると、毎日眺めて「まだ大きくならないのか」と気をもむばかりになる。ところが山に植えた場合、常に見ることはできないため、時折訪れてみると、いつの間にか大きく育っていることに気づく。大事なものを育てるには、ゆったりとした気持ちで臨むべきだという教えである。
株式投資にも通じる言葉である。信念をもって選んだ銘柄なら、日々の株価に一喜一憂せず、山に植えた木のようにしばらく見守ることで、気づいたときには大きく値上がりしていることもある。
筆者が子どもの頃、祖母から「モチは女に焼かせ、魚は旦那に焼かせよ」と教えられたことがある。理由を尋ねると、祖母は「モチは焦げないように頻繁にひっくり返す必要があり、魚はじっくり焼くものだから」と説明してくれた。腹をすかせて魚を何度もひっくり返していた筆者をたしなめる意味だったのだろう。男はどっしり構えるものだと子どもながらに感じた記憶がある。
株式投資にも、モチを焼くような短期投資と、魚を焼くような長期投資がある。重要なのは、自分がどちらの投資をしているのかを明確に意識することだ。これを混同すると損をしかねない。情報が絶えず流れ、手数料が安くなったネット取引では、モチを焼くような機敏さが求められる。一方、長期投資では焦りは禁物である。
かつては情報量も少なく、ネット取引もなく、手数料も高い時代であったため、長期投資が主流だった。相場の位置を見極め、景気や企業業績を先読みしたうえで投資するのが一般的で、まさに「木を庭に植えず山に植えよ」の姿勢だった。現在でも有効な考え方だが、昔の長期投資が10年規模であったのに対し、いまは2〜3年が目安になっている点には注意が必要である。
経営の現場でも同様に、製品ライフサイクルの短縮によりスピード経営が求められている。社会資本の充実や耐久消費財の普及率上昇、多様化する消費者の嗜好などにより、ゆったりした経営では対応が難しい局面も増えている。モチを焼くような感性を持つ女性の活躍が今こそ必要であり、経営の意思決定層に女性を登用する意義は大きいといえる。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)