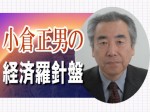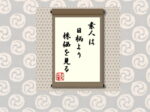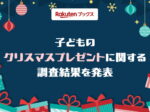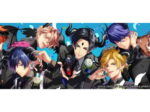- Home
- 小倉正男の経済コラム
- 【小倉正男の経済羅針盤】原油価格急落=「デフレの時代」に突入か
【小倉正男の経済羅針盤】原油価格急落=「デフレの時代」に突入か
- 2014/12/13 06:00
- 小倉正男の経済コラム
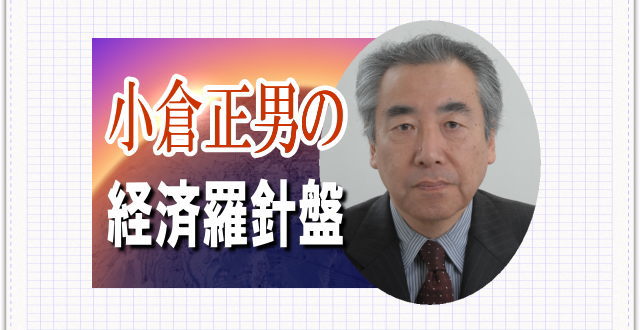
■1バレル=60ドル台割れに急落した原油価格
原油価格の低迷が止まらない。ついには1バレル=60ドル台(NY原油先物市場)を割り込むといった事態となっている。今年最高値は1バレル=110ドル台(6月)だったわけだからほぼ半値に近い低落となっている。
新年にはさらに下がり、「30ドル原油」、あるいは「40ドル原油」になるという予測も出ている。
「石油ガブ飲み」といわれた中国経済が失速している。ユーロ圏経済も、ギリシャなど南欧諸国の低迷・混迷が続いており、大底からの脱出が遅れている。
しかもOPEC(石油輸出国機構)とアメリカのシェールオイルとの競合関係が激化している。需給面でも供給過剰の傾向が顕著になっている。
■OPECが「骨身を切る戦略」に踏み切る
これまではサウジアラビアなどOPEC諸国は、シェールオイルを無視するというか、ほとんど問題視しないできた。しかし、シェールオイルのシェア拡大に対して、OPECは戦略を一変させた。
OPECは需要低迷に対応する減産は行わないことを決定した。
OPECは、あえて原油価格の低迷を容認することで、シェールオイルの生産・供給拡大にストップをかける方針を打ち出したことになる。
OPECとしては、原油価格低迷という「骨身を切る戦略」を採用し、アメリカのシェールオイルの生産・供給体制に打撃を与えるのが狙いである。
OPECはれっきとしたカルテルの塊だ。そのOPECが皮肉にも、当面はカルテル体制を守るために、あえて競争に挑んだようなものである。
OPECは、中長期では、世界の景気回復動向などを睨み、シェールオイルとの調整を進めて、再び原油価格の高騰を図るのが究極の意向とみられる。ただし、供給過剰が事実として判明している以上、原油価格が再上昇するかどうか、いまや不透明でしかない。
■第1次~第2次オイルショックはOPECの勝利
第1次オイルショックは、1970年代前半~70年代央のことだが、原油価格が1バレル=3ドルから5ドルになり、ついには11ドル台に騰がったことで勃発した。
日本では、店頭からトイレットペーパー、洗剤がなくなるような騒ぎとなり、インフレが加速された。まさに「狂乱物価」の時代だった。原材料価格高騰でコストは上昇したが、製品価格へのコスト転嫁が進んだ。
第2次オイルショックは、1970年代末から1980年前半に原油価格が1バレル=18ドルから30ドル台に上昇したことによるものだ。
原材料コストは上昇したが、製品価格には転嫁が進まなかった。企業は、「原材料高・製品安」の苦境に陥った。スタグフレーションが進行し、企業は不況にあえいだ。全体にモノ余りというか、供給過剰の時代に突入していたことによる。
第1次オイルショックの勃発時には原油価格は1バレル=3ドルだったが、それ以前は1バレル=1ドル程度だった。それが30ドル台になった。OPECの圧倒的な勝利だった。
■本格的な「デフレの時代」が到来する
2000年代になると原油価格は100ドル台に上昇した。これは「第3次オイルショック」というべきもので、「石油ガブ飲み」の中国経済が台頭したことが最大の要因だ。中東諸国の政治的な混迷も100ドル台といった原油価格に拍車をかけた。
この超高騰価格は、OPECにはタナボタのお客が出現した恩恵だった。しかしその反面であまりの超高騰価格は、アメリカのシェールオイル開発・供給を促進させた。
これだけの美味しいマーケットに指をくわえて手を出すなというわけにはいかなかった。
原油価格は、どこまで下がるのか。1バレル=30ドル~40ドルに下がるとすれば、懸念されるのがデフレである。
原材料価格の低下は、コストを低減する。最終製品価格が下がらなければ、利益が生み出される。しかし、世界全体が供給力過剰の状況にあり、原材料コスト低減は、製品価格を押し下げることになる。
企業でいえば、売り上げが下がり、利益が下がることになる――。景気は悪化が避けられない。
今回の原油価格の急低下は、「オイルショック」とまったく正反対、本格的な「デフレの時代」の到来をもたらすということになるのでないか。
(経済ジャーナリスト・評論家、『M&A資本主義』『トヨタとイトーヨーカ堂』(東洋経済新報社刊)、『日本の時短革命』『倒れない経営』『第四次産業の衝撃』(PHP研究所刊)など著書多数)