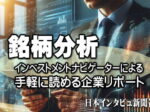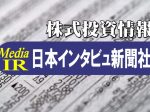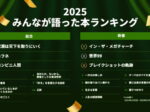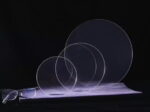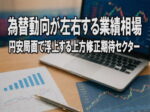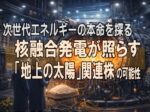ピックルスホールディングス、26年2月期中間期大幅増益で通期再上振れの可能性、販売価格適正化と原価安定化が奏功
- 2025/10/16 07:30
- アナリスト銘柄分析

ピックルスホールディングス<2935>(東証プライム)は漬物・キムチ製品の最大手で、独自の乳酸菌Pne-12を使用した「ご飯がススムキムチ」シリーズや惣菜を主力としている。成長戦略として製品開発強化、販売エリア・販売先拡大、販売価格適正化や原価低減による収益性向上などを推進し、野菜・発酵・健康の総合メーカーを目指して外食・小売・農業領域への展開も推進している。26年2月期は大幅増益予想(9月22日付で上方修正)としている。中間期の進捗率が高水準であることを勘案すれば、通期会社予想は再上振れの可能性が高く、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。株価は9月の年初来高値圏から反落し、地合い悪化も影響して上げ一服の形となったが、1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。
■漬物製品の最大手で「ご飯がススムキムチ」シリーズや惣菜が主力
漬物・キムチ製品の最大手で、独自の乳酸菌Pne-12(ピーネ12)(特許取得済)を使用した「ご飯がススムキムチ」シリーズや惣菜などを主力としている。さらに野菜・発酵・健康の総合メーカーを目指して外食・小売・農業領域にも展開し、子会社OHが埼玉県飯能市に複合型観光施設として発酵のテーマパーク「OH!!!~発酵、健康、食の魔法!!!~」を運営している。
また22年3月には、子会社ピックルスファームを設立して埼玉県内で農業事業を開始した。野菜の生産に関わることで安全・安心な原料野菜を安定的に調達するとともに、農業を通じた雇用創出や地域活性化にも貢献することを目指す。23年9月には、センシングデバイスや農業資材などを取り扱う複合機能商社であるAsueとの合弁により、さつまいもを原材料とする加工食品の仕入・販売を行う子会社ベジパル(出資比率60%)を設立した。
生産面では24年12月に茨城工場(投資額約50億円)が本格稼働した。関東全域の「ご飯がススムキムチ」シリーズを生産し、稼働後の時間あたり生産効率は従来工場比で約2倍に向上する。今後の取り組みとして、東北エリア分を生産する宮城ファクトリー、中京・北陸エリア分を生産する中京工場の生産分を引き受け、年間を通じて安定した生産体制の構築と生産能力の最大化を推進する。また、その他の工場における生産効率化の取り組みとして、所沢工場の専用ラインをグループ会社の手柄食品(兵庫県姫路市)に移管し、西日本エリアにおける「ご飯がススムキムチ」シリーズの生産能力・製造効率の向上を推進する。
25年2月期の品目別売上構成比は製品69.1%(浅漬・キムチ40.4%、惣菜27.8%、ふる漬0.9%)および商品(漬物、調味料、その他)30.9%、販路別売上構成比は量販店76.4%、コンビニ15.6%、外食・その他8.0%だった。セブン&アイ・ホールディングス<3382>など大手量販店・コンビニが主要取引先である。収益面の特性としては、個人消費動向のほか、天候不順などによる野菜(特に胡瓜と白菜)価格の影響を受ける傾向がある。
■成長戦略として新規領域での売上創出を推進
中期経営目標値(ローリング方式により1年ごとに見直し)としては、28年2月期売上高430億円(浅漬・キムチ178億03百万円、惣菜118億10百万円、ふる漬4億69百万円、商品129億17百万円)、売上総利益88億99百万円、売上総利益率20.7%、販管費71億99百万円、販管費比率16.7%、営業利益17億円、経常利益17億70百万円、親会社株主帰属当期純利益11億30百万円を掲げている。
成長戦略としては、売上面では既存領域で拡販を推進しながら、新規領域で10億円超の新たな売上創出(「OH!!!」事業+海外市場開拓で5億円規模、さつまいも商品+業務用冷凍関連製品+健康志向製品で8億円規模)を目指す。また収益性向上策として、小ロット生産・不採算製品を中心とするアイテム数の絞り込み、原価上昇と連動した販売価格見直し、生産体制の効率化・自動化、原材料調達の見直し・効率化などを推進する。なお販売価格見直しについては25年5月より主力製品の販売価格改定と内容量変更を同時に実施した。設備投資は26年2月期からの3年間で合計30億円(26年2月期14億円、27年2月期9億円、28年2月期7億円)を計画している。株主還元については累進配当に変更した。
SDGsへの取り組みとしては、太陽光発電の導入、LED電灯の100%導入、子ども食堂への支援、オリジナルエコマーク「ピックルスのECO」の導入などに加えて、野菜残さを餌としたウニの養殖研究にも取り組んでいる。23年2月には健康経営宣言を策定した。25年3月には健康経営優良法人認定制度において健康経営優良法人2025(大企業法人部門)に認定された。
なお25年2月末時点でプライム市場の上場維持基準のうち流通株式時価総額が不適合となったため、25年5月28日付で上場維持基準の適合に向けた計画をリリースした。基本方針として、28年2月期を最終年度とする中期経営計画の達成に向けた戦略の実行やIR活動の強化などにより、株価を向上させることで流通株式時価総額を増加させる。また流通株式時価総額の向上のために、さらなる流通株式数の増加を図ることも検討する。
■26年2月期は上方修正して大幅増益予想、さらに再上振れの可能性
26年2月期の連結業績予想(25年9月22日付で上方修正)は売上高が前期比0.4%増の417億円、営業利益が62.6%増の20億80百万円、経常利益が59.8%増の21億50百万円、親会社株主帰属当期純利益が50.3%増の14億40百万円、EBITDA(営業利益+減価償却費)が44.3%増の32億96百万円としている。配当予想(25年9月22日付で第2四半期末2円上方修正)は前期比3円増配の29円(第2四半期末15円、期末14円)としている。連続増配で予想配当性向は25.2%となる。
売上高の計画は、品目別には製品が1.3%増の290億82百万円(浅漬・キムチが0.4%減の167億02百万円、惣菜が3.9%増の119億96百万円、ふる漬が2.1%減の3億84百万円)で商品(漬物、調味料、その他)が1.5%減の124億60百万円、販路別には量販店が2.6%減の309億12百万円、コンビニが13.7%増の73億49百万円、外食・その他が3.9%増の34億38百万円としている。
売上面は消費者の節約志向の影響などで小幅増収にとどまるが、利益面は野菜の仕入価格安定化による製造経費減少、アイテム数絞り込みなど収益性向上に向けた製品ポートフォリオ見直し効果、業務効率化による販管費抑制などが寄与して大幅増益予想としている。重点施策として、営業面は各種キャンペーンなど効果的な販促活動、商品規格や販売価格の見直しによる値上げ、新規取引先の開拓や既存取引先の深耕、製造面は製品の集約、不採算アイテムの見直し、省力化などによる生産コスト改善、新規稼働した茨城工場における効率的な製造、原料調達面では契約栽培の拡大による安定調達、産地の分散化などを推進する。
第2四半期累計(中間期)は、売上高が前年同期比2.9%増の223億21百万円、営業利益が40.5%増の15億69百万円、経常利益が38.5%増の16億23百万円、親会社株主帰属中間純利益が38.1%増の11億02百万円、EBITDAが37.4%増の21億39百万円だった。
計画を上回る増収・大幅増益(25年9月22日付で上方修正)だった。コンビニエンスストアが実施したキャンペーン効果などによる増収効果に加え、製品価格改定や値引き抑制などの販売条件適正化、原料野菜仕入価格の安定推移、業務効率化による労務費・物流費の抑制などが寄与した。
売上高の内訳は、品目別には製品が6.7%増の158億08百万円(浅漬・キムチが3.9%増の86億82百万円、惣菜が11.1%増の69億47百万円、ふる漬が14.8%減の1億79百万円)で商品(漬物、調味料、その他)が5.3%減の65億13百万円、販路別には量販店が3.2%減の161億36百万円、コンビニが28.4%増の41億61百万円、外食・その他が13.1%増の20億23百万円だった。
全社ベースの業績を四半期別に見ると、第1四半期は売上高が110億38百万円で営業利益が6億19百万円、第2四半期は売上高が112億83百万円で営業利益が9億50百万円だった。
通期予想(修正後)に対する中間期の進捗率が売上高54%、営業利益75%、経常利益75%、親会社株主帰属当期純利益77%と高水準であることを勘案すれば、通期会社予想は再上振れの可能性が高く、積極的な事業展開で収益拡大基調だろう。
■株主優待制度は毎年2月末の株主が対象
株主優待制度(詳細は会社HP参照)は毎年2月末時点の100株(1単元)以上保有株主を対象として商品詰め合わせセットなどを贈呈する。
■株価は上値試す
株価は9月の年初来高値圏から反落し、地合い悪化も影響して上げ一服の形となったが、1倍割れの低PBRなど指標面の割安感も評価材料であり、利益確定売りをこなしながら上値を試す展開を期待したい。10月15日の終値は1133円、今期予想連結PER(会社予想の連結EPS115円15銭で算出)は約10倍、今期予想配当利回り(会社予想の29円で算出)は約2.6%、前期実績連結PBR(前期実績の連結BPS1482円42銭で算出)は約0.8倍、そして時価総額は約146億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)